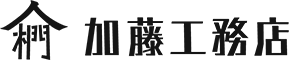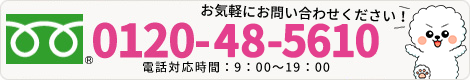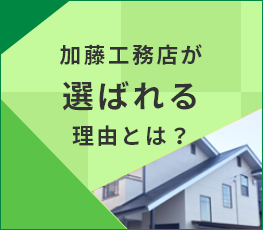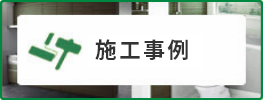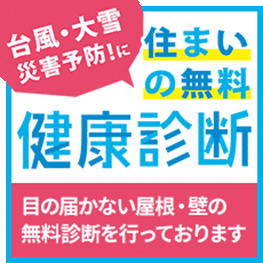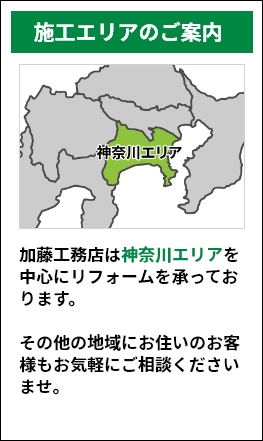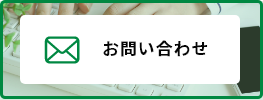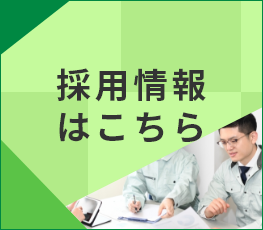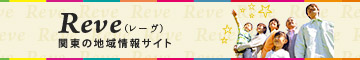こんにちは、加藤工務店です。
ついこの前まで暑かったのに、秋の深まりを感じる今日この頃となりました。みなさまいかがお過ごしでしょうか?

これから年末に向けて少しずつ慌ただしくなる時期ですね。そろそろ「年末調整」の書類提出が頭をよぎる方も多いのではないでしょうか。
実はこのタイミングこそ、住宅リフォームにまつわる“減税制度”をチェックする絶好の機会。
「制度が多くてよく分からない…」と後回しにしがちな税制優遇も、知っておくだけで節税に役立つことがあります。
今回は、年末調整と一緒に考えたい「住宅リフォーム減税」について、2025年版の情報をわかりやすくお届けします。
住宅ローンを使ったリフォームも対象に!「住宅ローン減税」の基本

住宅購入だけでなく、一定の条件を満たせばリフォームや増改築にも適用できるのが「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」です。
2025年現在の制度では、次のような要件があります。
<主な適用条件>
- □自分が住む住宅であること
- □床面積が50㎡以上(合計所得金額が1,000万円以下の場合は40㎡以上も可)
- □リフォームローンの返済期間が10年以上
- □合計所得金額が2,000万円以下
- □工事が増改築や修繕などの対象要件を満たすこと
この条件を満たせば、年末のローン残高の0.7%を最大10年間、所得税や住民税から控除できます。
たとえば1,000万円のローンを利用した場合、年間7万円の控除が10年間受けられる計算です。
ローンを組んでリフォームを行う予定がある方は、早めに条件を確認しておくと安心です。
ローンを使わなくても減税対象!「リフォーム促進税制」

ローンを組まない現金リフォームでも、一定のリフォーム内容であれば減税を受けられる制度があります。それが「リフォーム促進税制」です。
対象となる工事には以下のようなものがあります。
<主な対象工事>
- □耐震改修:耐震基準を満たすための工事
- □省エネ改修:断熱窓・節水設備・高効率給湯器など
- □バリアフリー改修:手すり設置・段差解消・浴室改修など
- □三世代同居対応工事:キッチンや浴室を複数設ける工事
これらの工事を行った場合、工事費の10%が所得税から控除されるケースがあります(上限額あり)。
また、固定資産税の減額措置が受けられる場合もあり、自治体によっては独自の補助金や上乗せ制度が用意されているところもあります。
さらに、このリフォーム促進税制は「2025年12月31日まで」が期限とされているため、今がちょうど活用しやすい時期です。
年末調整・確定申告で注意したい3つのポイント

減税制度を上手に使うには、年末調整や確定申告の手続きも忘れずに行う必要があります。
次の3つを押さえておきましょう。
① 申告時期を確認する
住宅ローン減税は、初年度は確定申告が必要です。2年目以降は会社員なら年末調整で手続きが可能です。
② 必要書類をそろえる
リフォーム促進税制を利用する場合、
・工事証明書(施工業者発行)
・領収書や契約書の写し
・住宅の登記事項証明書
などの提出が必要です。
③ 工事内容が対象かを事前に確認する
制度の対象となる改修工事には要件があるため、「工事前の相談」がとても大切です。リフォーム後では適用が難しくなるケースもあります。
リフォーム内容によって使える制度を選ぼう

リフォームを考える際、「ローンを使って非住宅リフォームをする」「ローンを使わず省エネ・バリアフリー改修を行う」という二つの選択肢が見えてきます。どちらが得かは、工事内容・費用・居住状況・収入状況などによって変わります。例えば、ローン型控除を使えば10年間にわたって控除を受けられるケースがありますが、ローンを組めない状況では促進税制を検討するというのもひとつの手段です。
どちらを使うか迷ったときは、リフォーム会社や税理士に相談しながら、自分の住まいや家族の状況に合った制度を選ぶことをおすすめします。
リフォームを検討している方は、申請期限や要件をしっかり確認して、上手に活用してみてくださいね。
※ブログに記載された情報は、2025年10月現在のものですが、制度等の内容については随時変更等が生じる可能性がございますので、あらかじめご了承ください。詳細については各行政機関等のHPなどでご確認ください。